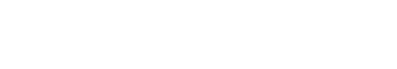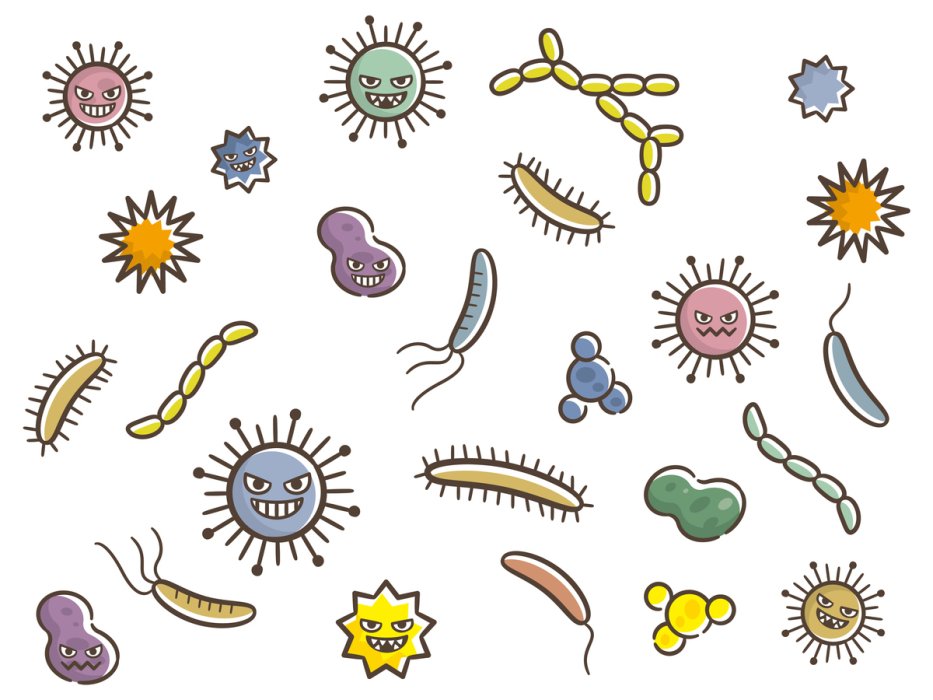
2025/06/01 コラム
食中毒に注意
我々は日々様々な食品を口にしています。
野菜や肉などの食材を購入し家で調理する場合や、総菜や弁当などの調理済の食品を購入し家庭で食べること、レストランやファストフード店で外食するなど食事を行うことによって生命活動を維持しています。
このように当たり前のように食事ができるのは、食品の安全性が担保されているからです。
しかし、食品の安全性が十分に確保されなかったために、食中毒が発生することが時折起きています。
食中毒は様々な場所で発生していますが、令和4年度(2022年)の厚生労働省発表の食中毒発生状況(概要版)によると、飲食店が全体の39.5%、次いで家庭が13.5%と続いており、飲食店や家庭での発生が全体の50%を超えています。
一方、発生場所が特定できない不明の件数も30%程度発生しており、そういったケースも多いことが伺えます。
食中毒のほとんどは一過性で症状が軽いものも多いですが、時に重篤となるケースがあり、入院をしなければならないこともあります。
食中毒の原因を件数でみると、加熱不十分な鶏肉や生の鶏肉の喫食によって感染しやすいカンピロバクターによる食中毒、主に二枚貝に蓄積されやすいノロウイルスを原因とする食中毒が多く、ついで近年は寄生虫の一つでアイナメやアオリイカなどの魚類に寄生するアニサキスによる食中毒も多く発生しています。

食中毒は、原因となる細菌などが生息する食材を喫食することによる感染だけでなく、調理者が原因となる細菌などを保菌している場合や、調理の過程で原因細菌を他の食材へ移してしまうことによる調理過程での感染も問題となっています。
調理過程による感染は家庭における調理でも生じるため十分注意する必要があります。
厚生労働省が推奨する細菌性食中毒予防の3原則は、
細菌を食べ物に「つけない」、
食べ物に付着した細菌を「増やさない」、
食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」であり、
ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒予防に関しては、
ウイルスを調理場内に「持ち込まない」、
食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」、
食べ物にウイルスを「つけない」、
付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」
の4原則を啓発しています。
細菌性やウイルス性の食中毒は、いずれも食材の十分な加熱で防げます。
表面は加熱できているように見えても中心がまだ加熱不十分の場合もあるので、家庭で食材を調理し喫食する場合は、中心まで食材を加熱するようにしましょう。
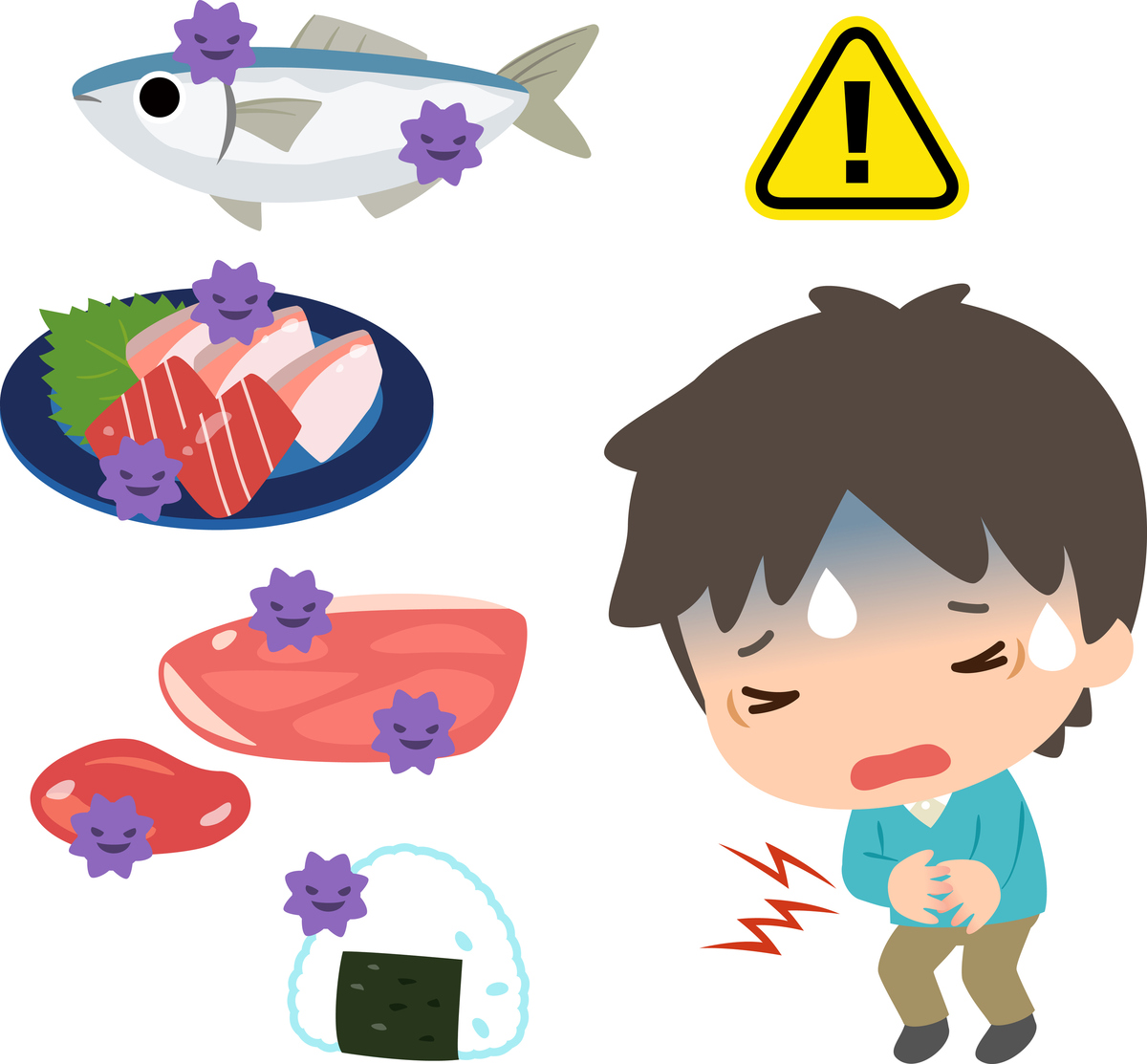
参考文献
厚生労働省発表 令和4年食中毒発生状況(概要版)
厚生労働省ホームページ:家庭での食中毒予防 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00008.html